貯蔵・輸送技術が発達していない江戸時代、活きの良い魚をおかずにできるのは江戸っ子の特権で、大変贅沢なことです。ちょっとへんぴな所だったら、塩漬けや干物などに加工しないと、すぐ悪くなってしまいます。庶民の食事といえば、たくあん、ひじきと豆を煮たもの、豆腐など。魚が食卓にのぼる日といったらご馳走です。魚には下等・上等とランクがあり、庶民と金持ちでは食べることができる種類は異なります。落語はその対比が面白おかしく描かれており、『さくら鯛』『青菜』『芝浜』『目黒のさんま』『寄合酒』五つの落語を紐解き、魚という切り口から人々の暮らしぶりを覗いてみましょう。
第一話 さくら鯛
殿様の御膳にあがる魚といえば「鯛」
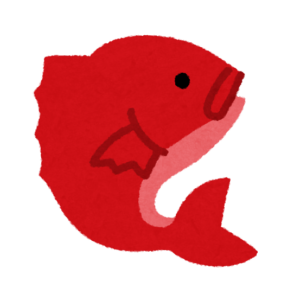
鯛は今も昔も高級な魚の代表格です。殿様の贅沢な食生活が伺える『さくら鯛』という噺があります。殿様には高級な魚を献上しなければならないと、毎日食事に鯛の塩焼きが給仕されています。
ただ毎日鯛が続くので、さすがに殿様も飽きてしまい、普段はめったに箸をつけません。
しかしその日は一箸つけ、しかも「代わりを持て」との仰せで台所係はびっくりです。家来の絶妙な機転でその場を切り抜けます。
「殿様、お庭の桜がきれいに咲きました」
殿様の目が桜にいっている隙に鯛を裏返し、「代わりを持ってきました」としました。しかし、また一箸だけつけて、「代わりを持て」と言うもんだから、家来も困り果てていると、今度は殿様が機転を利かせて一言。
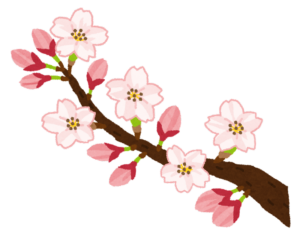
「また、桜でも見ようか」
殿様には必ず毒見役がついていますから、出来立てなんて食べられません。どんなに上等な鯛の塩焼きだって、冷えちゃってカチカチ、そんなに美味しいものじゃなかったかもしれません。しかも毎日同じような献立です。だから、普段は箸をつけなかったのではないかと考えられます。とっさの家来の閃きもお見事ですが、殿様の助け舟がなんとも面白い。
真鯛の中でも、桜が咲く頃に産卵期を迎え、鮮やかな桜色をした鯛のことを、特に瀬戸内海岸では「桜鯛」などと呼びます。春の訪れを感じさせる食材として大変珍重されたようです。殿様が桜を愛でながら食した鯛も、その桜鯛だったかもしれません。なんとも風流な一席ですね。
第二話 青菜
お金持ちと庶民では食べる魚がちがう

庶民が食べる下魚といえば「イワシ、あじ、さんま」など、金持ちが食べる上等な魚といえば「鯛、鰹、鯉」などです。当時、庶民の食卓に魚がのぼること自体、大変贅沢なことでした。庶民と金持ちの対比を、魚を用いて描いた『青菜』という噺があります。
旦那「鯉の洗いがある。よかったら、おあがんなさい。」
植木屋「しこしこして旨いもんですな」
旦那「淡白なものであって、冷やしてあるのが値打ちで、下に氷が入れてある」
植木屋「氷をひとつ頂戴します。この氷は冷えてますな」
真夏のある日、ひと仕事を終えた植木屋に、大家の旦那が労いで柳蔭(やなぎかげ)と鯉の洗いをすすめます。鯉の洗いとは、シャボンで洗ったという意味ではなく、刺身のことです。氷の上にのせられて振舞われ、その冷たさこそが贅沢です。氷を口に含む仕草はなんとも美味しそうで、涼も感じさせます。
旦那はさらに青菜はいかがとすすめ、手を叩き台所にいる奥方を呼びます。すると奥方は『鞍馬(くらま)から牛若丸が出でまして、その名を九郎判官(くろうほうがん)』と言いました。旦那は『義経にしておきなさい』と返事しました。植木屋はさっぱり訳が分かりません。解説すれば、「青菜は食べてしまってもうない」ということを『その菜を食らう(九郎)判官』と言い表した奥方。対して旦那は、『よしておきなさい』と言うところを『義経にしておきなさい』、つまり旦那夫婦は、源義経にかけた洒落言葉でやり取りしたという訳です。
感心した植木屋は長屋に飛んで帰り、女房に教えます。そこへ、ちょうど友人がやってきます。さっそく旦那夫婦の真似事をしようとするが、小さい庶民の長屋には座敷と台所を隔てるものなどなく、女房を呼び出すところがうまく再現できません。困った植木屋は、女房を押し入れに放り込んでしまいます。柳蔭と鯉の洗いは、有り合わせの安い酒とイワシの塩焼きで代用し、青菜は嫌いだと言うところ無理強いし、手を叩き女房を呼ぶ。汗だくになった女房が押し入れから出てきて一言。
女房「鞍馬から牛若丸が出でまして、名も九郎判官義経」
植木屋「…弁慶にしておけ」
女房が肝心な台詞まで全部言ってしまい、義経と言おうと構えていた植木屋は困った末、捻りだした返事は義経に対して「弁慶」でした。庶民と金持ちの生活の違いが、鯉の洗いとイワシの塩焼きで置き換えて表現され、食す魚からも人々の暮らしぶりを窺い知ることができますね。
用語解説
●下魚(げうお)・・・庶民が食べられるような安い魚のこと。特に、イワシやさんま、あじ、さばなどが愛されていた。
●柳蔭(やなぎかげ)・・・みりんと焼酎を割合わせた飲み物。上方では柳蔭、江戸では直しと呼ばれていた。
●九郎判官(くろうほうがん)・・・源義経は、幼少期鞍馬寺に預けられ、牛若丸と呼ばれていた。その後、判官という職を拝受して、「九郎判官」と呼ばれていた。
第三話 芝浜
魚河岸の朝は早い!
魚の行商を「棒手振り」といい、天秤棒を担いで商いをしていました。昔、今のような冷蔵技術や輸送手段なんてありません。魚屋は早起きして、なるべく早く魚を仕入れて得意先へ届け、鮮度がいいうちに食べてもらう。これが、商売の評判を上げるコツです。
朝の魚河岸は一日で千両動く
夜の吉原と並んで、朝の魚河岸はそう謳われるほどの盛況ぶりだったそうです。魚河岸はとにかく朝が勝負で、喧嘩っ早い江戸っ子で賑わいます。「何してんだこんちきしょう」のような、売り言葉に買い言葉が飛び交うのも当たり前です。
『芝浜』という落語は、大酒呑みで怠け者の勝っつぁんという魚屋と、その女房との夫婦愛を描いた屈指の人情噺です。芝浜とは現在のJR田町駅あたりが海岸線だった頃、近海物の魚市があったところで、「芝肴(しばざかな)」と呼ばれる活きの良い魚に江戸っ子は舌鼓を打ちました。

酒を飲んでは仕事を怠ける夫に、今日こそ仕事に行ってもらわなきゃと、しびれを切らした女房は、ついつい早く起こし過ぎてしまいます。これが、夢のような話の始まりだったのです。早起きし過ぎて魚河岸の問屋はまだ開店していません。しょうがない、浜辺で夜明けを待っていると波打ち際に落ちていた財布を見つけ、中に大金が入っています。家へ飛んで帰り、これで遊んで暮らせると、友達を呼び集めてまた酒を飲み、寝てしまいました。
翌朝、商いに行けと女房にたたき起こされた勝っつぁん、浜辺で拾ったお金のことを話すと、「夢でも見たんでしょう」と言われます。金を拾ったのは夢で、友人とドンチャン騒ぎして散財したのが現実だと聞かされ、すっかり改心します。禁酒を誓い、商いに精を出した甲斐があって、三年目には小さい店を構えるようになりました。大晦日の除夜の鐘を聞きながら、女房が腹を立てずに聞いておくれと話を切り出します。「三年前、夢だと言ったのは嘘なんだよ・・・」と、浜辺で拾った財布を夫の前に差し出し謝ります。落とし主が分からないお金で飲んでは罪になると思い、お上に届けたのだという。結局落し主は見つからず、お金は戻ってきたのです。泣きながら打ち明ける女房に、勝っつぁんはかつての自分のふがいなさを思い出し、また女房の深い愛情に心を打たれ、怒るどころか礼を言います。「おまえさん一杯飲むか?」と久々に酒をすすめられるが、ちょっと待てよと踏み留まり・・・。
「よそう。また、夢になるといけねぇ」
『芝浜』は、三代目桂三木助が東京から消えゆく江戸の風情を残そうと、当時の江戸湾(現 東京湾)沿いにあたる、芝の浜を舞台にして大成させた落語です。夢と現実が交差する中で、夫婦の情けがほろっと涙を誘う、心に染み入る噺です。
第四話 目黒のさんま
秋の味覚といえば、やっぱりさんま
旬を頂くということは贅沢なことで、昔は今よりずっと旬を大切にしていました。脂の乗ったさんまを炭火で焼き、あふれ出て落ちる脂は堪りません。さんまは秋にうんと獲れたので安価で、下魚の類に入る庶民の味です。『目黒のさんま』という噺に登場する殿様は、もちろん食べたことがありませんでした。

ある秋の日、殿様が馬術鍛錬のため家来を連れて目黒へ出かけました。お腹が減った時、百姓の家でさんまを焼くいい香りが漂ってくるので、思わず食べたくなります。家来は「殿様のお口に合うものではございません」と申し上げるが、殿様は「旨い旨い」と五~六匹もたいらげてしまいました。さんまを大層気に入り、その味を思い出しては食べたがっていました。ある日、親類の大名家に呼ばれ、何でもお好きなものをと言われ、さんまを注文しました。だが、大名屋敷の台所に庶民の魚であるさんまなど置いてある訳がありません。慌てて魚河岸から一番上等なのを取り寄せ、脂は体に悪いからと蒸してすっかり抜き、骨も一本一本抜いてお出ししました。醍醐味を台無しにされたさんまは、全く美味しくありません。
殿様「いずれから取り寄せた?」
家来「日本橋の魚河岸でございます」
殿様「それはいかん、さんまは目黒にかぎる」
世間知らずな殿様は、いつかの目黒で食べたさんまの味が忘れられず、海とは無縁な目黒で採れたものが美味しいんだと信じ込んでいるというオチです。噺に描かれているさんまは、金網など一切使わず炭火の中にそのまま突っ込んで焼かれます。庶民の流儀で無造作に調理した方が美味しく、むしろ殿様用に丁寧に調理したら不味くなっちゃったという滑稽な話です。
第五話 寄合酒
江戸っ子大好き、初鰹!
「武士・鰹・大名小路・広小路・茶店・紫・火消・錦絵・火事に喧嘩に中っ腹・伊勢屋・稲荷に犬のくそ・・・これが江戸の名物でございます」と、枕でよく聞く決まり文句です。江戸っ子は初物を好み、特に四月初日以降に出回る初鰹を珍重し、江戸名物にも挙げられています。高値をつけて争ってでも買い求めたそうです。いったい、いくらぐらいだったかというのは、落語『白子屋政談』が原作である『髪結新三』という歌舞伎の有名なワンシーンから窺い知ることができます。「小悪党髪結の新三は、娘のお熊を誘拐し手に入れた身代金の半額十五両を、家主の長兵衛に持ってかれてしまうだけでなく、金三分をはたいて買った初鰹の半身も持ってかれてしまう」と描かれています。金三分とは今の値段でいう七~八万円に相当すると推察されます。とにかく、江戸っ子は初鰹には目がなかったのです。江戸時代後期頃の三都(江戸・京都・大坂)のくらしの様子を綴った風俗誌『守貞漫稿』にも、四月一日に食べる初鰹には一尾金二~三分ほどの値段をつけたとも記載されています。初鰹に大枚を投じるのは、江戸っ子の粋の一つとも言えるでしょう。
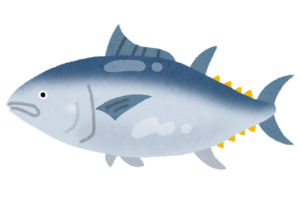
この粋な初鰹の対局にあたるような噺に、若い男たちが金を使わず材料持ち寄りで呑もうという、賑やかで笑い要素たっぷりの『寄合酒』が挙げられます。みんな金がないので、乾物屋をチョロまかして数の子やらかつお節やら干鱈、味噌など、あの手この手を使って食材を集めます。ここで、かつお節がまさかの珍騒動を引き起こします。ダシを持って来いと言うと、ダシがらの方を持って来ました。「違う、ぐらぐらと煮だした汁の方だ」と言うと、「あのお湯もいるんですか?」と、とぼけたことを言う。あの湯がいるんなら最初から言ってくださいな…
「もったいないなと思って、ひとまず手を洗って、たらいに開けて、褌をつけたとこや」
かつお節のダシがらの方を大事に取っておき、肝心なダシ汁で洗濯してしまうなんて、何とも馬鹿馬鹿しい話です。庶民のダシといえば、植物性なら昆布や椎茸、動物性でいえば煮干しと言った所でしょう。かつお節は庶民にとって高級品です。庶民はかつおダシの取り方なんて、案外知らない人も多かったんじゃないでしょうか。
用語解説
●髪結新三・・・明治期の歌舞伎の作品。梅雨小袖昔八丈」という作品の通称。季節感を芝居に出すために、初鰹を効果的に演出に利用している。








