江戸時代におやつを食べるという習慣が広まったとされ、「おやつ」は今でいう十四時から十六時までの「八ツ刻(やつどき)」に由来します。もとは、お菓子・果物・おにぎりなどの軽食、すなわち食事以外のすべての間食をひっくるめて「菓子(かし)」といいましたが、今でいうスイーツを「(お)菓子」と呼ぶようになったので、区別するために、果実類を上方では「果物(くだもの)」、江戸では「水菓子」と呼ぶようになったそうです。
本来、果物は日本の風物詩の一つとして、私たちに四季を感じさせてくれる食べ物です。
落語にも果物と季節をテーマにした噺があることから、果物は庶民の生活に季節感と彩りを添えたことが伺えます。
第一話 千両みかん
季節外れのみかんに恋い焦がれ…
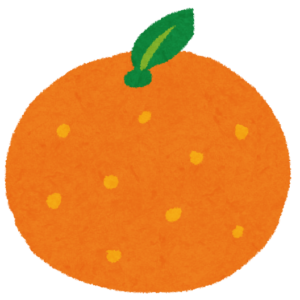
現代、農業の技術改良やハウス栽培、流通の発達などにより、一年中いろいろな果物が食べられる時代になりました。その反面、四季がある日本だからこそ楽しめる「旬」が分かりづらくなったのは悲しくもあります。そんな中でも、「冬はこたつにみかん」といったように、みかんは店頭に並ぶと冬の訪れを感じさせ、「旬」をしっかりと残している果物の一つです。昔は今と違い、季節によって桃なら桃、柿だけ、みかんだけのように、その季節の果物だけを売る「一色商い(ひといろあきない)」でした。振り売りといって、天秤棒を担いだ行商が市中を売り歩き、季節の味覚を運んでいました。「千両みかん」という噺は、「旬」のものしか味わえない江戸時代の暮らしぶりが伺える一席です。
若旦那の具合がどうもおかしい。さては恋煩いかと思って尋ねると「みかんが食べたい」。番頭は二つ返事で引き受けましたが、気が付くと季節は夏の盛り。みかんなど売っている訳がありません。江戸中を探し回って、ある青物問屋に幾箱か囲ってあり、中に一個だけ腐っていないみかんがありました。しかし、季節外れの商いとあって…
「みかん一個…千両になります。」
「いつなんどき買いに来られても、ありませんと断るのは商売の恥。腐るのを承知で囲っておきます。みんな腐ったら笑って諦め、一つでも残ればそれに腐った分をみなかける。
それが商売ってものではありませんか」千両には、商売人の言い分がちゃんとあるのです。江戸で演じる千両みかんは、神田にある果物問屋をモデルにしたと言われ、上方では天満にある青物問屋が登場します。江戸では野菜や果物を卸している青果市場は「やっちゃ場」と呼ばれ、神田、千住、駒込に江戸三大やっちゃ場がありました。季節外れであっても、神田や天満にあった大きな青物問屋だったら「うちでは、夏でもみかんがありますよ」という店があったかも知れません。
事の顛末は、旦那は息子の命が助かるなら安いと言って、みかん一個を千両で買います。若旦那は恋い焦がれたみかんを十房あるうちの七房食べ、残りは両親と番頭で食べてくれという。来年、暖簾分けの際に貰えるのはせいぜい五十両。それにひきかえ、このみかんは
一房百両、三房で三百両…血迷った番頭はみかん三房もってドロンしてしまったというオチです。若旦那も番頭も、たかがみかん一つに二人の男の人生が翻弄されてしまうは面白い。江戸っ子は旬、とくに初物といった季節ものに事弱い。そんな当時の人々の生き様に思いを馳せながら聞くと、より一層楽しめる噺ですね。
第二話 初天神
昔バナナは高級品だった
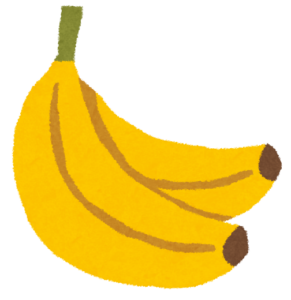
落語には生意気な子どもというのが多く登場し、「初天神」に登場する金坊もその一人です。初天神とは、菅原道真公を祀った天満宮で新年一月二十五日に開催される縁日で、果物や飴、お団子などの屋台が並び、多くの人々で大変賑わったようです。
新しく仕立てた羽織着たさに初天神に出かけた、お父ちゃんと金坊。あれこれねだらないという約束で連れてきたのに、今日はねだっていないから、そのご褒美に何か買ってちょうだいと言い出す始末です。果物の屋台を見つけては、やれリンゴを買えの、みかんを買えの、柿を買って…と、うるさい。
金坊「お父ちゃん、バナナ買って!」
父「バナナ、八十銭…、毒だ毒だ。」
金坊「お父ちゃんは、八十銭が毒なんだ…。」
リンゴやみかんは酸っぱいから毒、柿は体を冷やすから毒、あれこれ理屈を言って断るが、思わずバナナでは八十銭に反応してしまい、もちろん金坊は見逃してはくれません。
昔はバナナといえば高級品で、病気見舞いの時などでもなければ滅多に食べられるものではありませんでした。バナナは漢字で「甘蕉」と書き、古くは芭蕉(ばしょう)や実芭蕉(みばしょう)と呼ばれていました。「バナナは高いから毒だ」というのは、その言い方から明治以降のくすぐりだと言えるでしょう。大正・昭和以降はバナナとくれば、すぐ叩き売りを連想したものです。今ではその姿は見られなくなってしまいました。バナナの輸入は、日清戦争後、日本統治下に置かれた台湾から九州の最大の貿易港である門司港(福岡)を経由して神戸港へ輸入されたのが始まりと言われています。バナナは青い状態で輸入され、室(むろ)で蒸らし熟成させます。輸送中に熟れ過ぎてしまったり、傷んでしまう事があったので、その前に門司港で売り捌いてしまおうというのが、バナナの叩き売りの発祥とされます。その口上には、門司流と佐賀流の2つあり、的屋の叩き売りで有名な寅さんこと渥美清さんは佐賀の名人から習ったとも言われているそうです。結局バナナを買ってもらえなかった金坊はその後、飴玉、お団子、凧をねだって買ってもらいます。オチは、すっかり凧揚げに夢中になって糸を渡さない父親への痛快な一言です。
金坊「こんなことなら、お父ちゃん連れて来るんじゃなかった。」
第三話 佃祭り(つくだまつり)
虫歯を治す梨の信仰
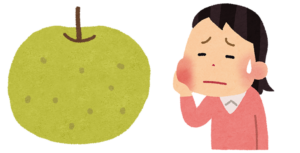
歯磨きという習慣は江戸時代に庶民の間でも定着しました。当時の歯ブラシは房楊枝といって、柳などの枝を細く削り、片方の先端を叩いてブラシ状にしたものです。江戸の男は白い歯にこだわりました。吉原に行っても、歯の手入れをちゃんとしていないとモテません。「親のすね かじる息子の 歯の白さ」なんて川柳もあり、独立もせず親に養ってもらっているような道楽息子は身なりを人一倍キレイにしていると皮肉っています。こんな若旦那は落語にもよく登場しますね。江戸時代、歯磨きの習慣があったとはいえ、虫歯率は高かったようです。歯医者はいますが、悪い歯は抜くか、薬を詰めて痛みを抑える程度で、虫歯の痛みだけはどうにも我慢ならなかったようです。
小間物屋(こまものや)の次郎兵衛さんは、佃島の住吉神社のお祭りを見に行った帰りに船に乗ろうとしたところ、女に引き留められ、乗り損なってしまった。訳を聞くと、三年前に吾妻橋から身投げをしようとしていたところを、次郎兵衛に助けられ、五両を恵んでもらったという。亭主が船頭だからいつでも帰れるというので、女の家で御馳走になることにしました。すると、表が騒がしくなり「おい、大変だ。船が沈んだ」という。因果応報、女を助けた恩が返ってきて、命拾いをしたのです。
さて、家では次郎兵衛が帰ってこないので、佃の渡しで死んだと大騒ぎ。そこへ、夜明けになって帰ってきたので一転大喜びです。次郎兵衛さんが助かった経緯を説明するのを聞いていた与太郎は、身投げを助ければ自分の命が危ない時も助けてもらえると信じ、五両をこしらえます。捜し歩くうちに、身投げの女を見つけ、助けようとすると…
女「歯が痛いから戸隠様に願をかけているのです」
与太郎「でも、着物の袂に石がいっぱい入っていらぁ。」
女「これは、納める『ありの実』でございます。」
長野の戸隠神社は虫歯の神様として有名で、梨を奉納し、梨断ちをすると虫歯が治るという信仰がありました。梨を「ありの実」と呼ぶのは、「無し」に通じることから嫌われた忌み言葉です。なぜ、梨の信仰が生まれたかは定かではありませんが、梨は酸が多く歯を溶かすからではないかという説もあります。願かけは、梨の実に生年月日とどこの歯が悪いかを書き、橋の上から戸隠神社を拝んで川に流します。その様子を遠くから見ると、与太郎が身投げと間違えたのは無理もないかもしれません。
第四話 あたま山
日本人は花見が大好き
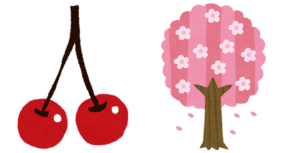
日本人は殊に桜を愛でる。花見の歴史は、もとは豊作祈願の行事として農民の間で行われていました。それが、八代将軍徳川吉宗が飛鳥山に桜の木を植えたことを機に、春の行楽として庶民の間にも広がり、今でいう桜の下でご馳走と酒を酌み交わす花見になりました。
観賞する桜はソメイヨシノという品種が多く、サクランボは実りません。サクランボが実る木の花はそれほど咲かず、品種は佐藤錦や高砂、ナポレオンなどが有名です。「あたま山」という噺は、サクランボを食べた事がきっかけで、SFのようなとんでもないストーリーへと展開します。
ケチで有名な男が花見に行きました。落ちているサクランボを拾って食べ、種を吐き出すことさえ惜しく飲み込んでしまいました。すると、体内のちょうどいい温度で芽を出し、男の頭を突き抜けて立派な桜の木に成長しました。そこへ、噂を聞きつけた花見客が集まってきて、ドンチャン騒ぎをするのでうるさくてたまりません。とうとう桜の木を引っこ抜いてしまいました。抜いた穴に夕立で水が溜まり、ボウフラがわく、フナ、鯉がわき、今度は魚釣りに大勢の人が集まり、またもやドンチャン騒ぎ。たまりかねた男は、自分の頭の池に身を投げてしまった、とさ。なんて現実味のない噺でしょうか。落語らしくはありませんが、歴とした古典落語です。今じゃ、サクランボは高級な果物になってしまいましたが、昔は酸っぱくて、小さくて、僕はそれほど好きではありませんでした。それに比べると、アメリカンチェリーなんかは、ずっと甘くて美味しかったことを覚えています。ただ値段は当時でも高かったようです。
第五話 紙屑屋(かみくずや)
江戸時代はエコ社会

紙、ろうそく、炭、女の髪の毛、古傘など、江戸時代は何でもリサイクルしたエコ社会でした。日本は紙使用大国で、古紙は回収し汚れ具合によって選り分け、再生紙にして使われました。紙屑拾いという職業までもあり、町中を歩き回って落ちている紙などを拾い、紙屑問屋へ持って行きます。紙屑問屋はそれらを仕分け、漉き返し業者へ売ります。再生紙にすることを「漉き返す(すきかえす)」といいました。「紙屑屋」という落語は道楽者の若旦那が勘当され、居候先に紹介された紙屑問屋で働く噺です。
主人が留守の間、屑の仕分けをすることなりました。根が遊び人のため、調子よく歌を歌って、仕事は捗りません。
「白紙は白紙~、カラスはカラス~、センコウ紙はセンコウ紙~、陳皮(ちんぴ)は陳皮~、毛は毛~」
恋文を見つけては夢中になって読み、川柳の本が出てくれば読み出す。今度は浄瑠璃の義太夫の本を見つけては、役者になった気分で芝居の真似事を始めてしまう始末です。そこへ主人が戻ってきて…
紙屑屋「何をやっているんですか?まったく、貴方は人間の屑ですね…」
若旦那「屑?今選り分けているところです。」
白紙は汚れのない白い紙、カラスとは墨で汚れた紙をいい、これらは漉き返して再生紙にされました。江戸の再生紙といえば浅草紙が有名で、庶民の日用紙として多く使われました。センコウ紙とは、刻み煙草の包み紙のことです。毛は女の髪の毛を集め、付け毛やカツラの材料にしました。陳皮とは、みかんの皮を乾かしたもので、漢方薬の材料です。風邪予防や胃や腸の働きを整える、発汗作用などがあります。みかんの皮には、香り成分であるリモネンが含まれるためリラックス効果もあります。また、陳皮は七味唐辛子の材料の一つでもあります。江戸時代のもったいない精神を、改めて現代人は見習わなくてはなりませんね。








