阿武松(おうのまつ)
~阿武松VSおまんまの敵!?

武隈親方の相撲部屋では、最近米の減りがやけに早い。新弟子の小車が犯人だと判明。この男、人間離れした大食い。
朝から、釜から赤ん坊の頭ぐらいのおむすびを17~18個作ってはぺろりと平らげ、さらに何杯おまんまを食べたかわからない。これでは部屋が食いつぶされてしまう。「大食いに大成するやつはいない」と言って1分の金を渡し、小車は破門されてしまいました。「面目なくて、故郷には帰れない」。せっかくなら、この金で最後に好きなだけおまんまを食べて、それから身投げをしても遅くないだろうと、旅籠に泊まることにしました。
一生の思い出に食うは食うは…二升入りのお櫃を三度取り換え、六升飯を食ってもまだ終わらない。
お相撲さんは食べることも修行の一環ですが、6升飯とは、いったいどれくらいなのでしょう。米の単位には、「合(ごう)」「升(しょう)」「斗」「石(こく)」「俵(ひょう)」があります。10合=1升、100合=1斗、1000合=1石となります。よって、6升=60合です。1合の米(約150g)は炊くことで約2.2倍に増えるため、ご飯340gです。
つまり、茶碗1杯を150gと考えると、小車が平らげた6升飯とは約140杯のご飯茶碗という計算になり、食い潰されると恐れても当然かもしれません。江戸時代、米はお金と同様の機能も果たしていました。武士の俸給は米の量を示す石高で表され、領地を石高で計算し、
1万石以上は大名、それ以下は旗本、御家人、下級武士などの身分に分けられました。武士の給料は領地としてもらう地方知行(じがたちぎょう)制度と、米で支給される俸禄制度があり、この米を蔵米(くらまい)と呼びます。下級武士には扶持米(ふちまい)という一種の家族手当のようなものがあり、家族の人数によって毎月米が現物支給されました。
1人1日当たりの生活費を男は5合、女は3合とし、例えば奉公人も含めて男女3人ずつの6人家族では、年間21.6俵(8.6石)が支給されました1俵=4斗=400合に当たり、米俵の重さは60kgです。給料は米で支給されても、生活するには現金が必要です。浅草の蔵前に札差(ふださし)と呼ばれる、旗本や御家人の代理人として蔵米を受け取り、現金にする両替業がありました。100俵につき1分の手数料を利益として差し引き、札差は銀行のような役目も果たし、贅沢の限りを尽くしたそうです。
噺の結末は、あまりの食べっぷりに旅籠の善右衛門は事情を聞き、それは気の毒な話だと、新しい親方を紹介してくれるだけでなく、米の面倒もみてやるから心配するなと言います。翌朝、錣山喜平次(しころやまきへいじ)の所へ連れて行かれ、体格を見るなり二つ返事で入門が決定。錣山親方の出世名・小緑というしこ名をもらい奮起。100日も経たないうちに番付を60枚以上飛び越える異例のスピード出世。クライマックスは、「おまんまの敵」武隈関と対峙します。この取り組みが長州候の目に留まって『阿武松緑之助(おうのまつみどりのすけ)』と改名。六代目横綱へと出世を遂げる、落語「阿武松」の一席です。
たらちね
~飯炊きは花嫁泣かせ~

始めチョロチョロ中パッパ、ジワジワどきに火を引いて、赤子泣くとも蓋とるな
最初はカンナくずなどを入れて小さな火で炊き、薪に燃えついたら吹き竹で吹いて、どんどん燃えるようにします。釜がジュウジュウ吹いてきたら、薪を外に出して、蒸らします。
どんなことがあってもふたを取っちゃいけない。飯炊きの極意を説明する、誰もが一度は聞いたことがある歌でしょう。とにかく、お嫁さんがまず苦労したのは、飯炊きを習得することでしょう。火加減もですが、水加減も難しい。私は昭和41年、仕事でメキシコに行くわけですが、向こうはインディカ米で、そのまま炊いたんじゃボソボソ。メキシコは標高が高いため、空気が薄くて圧力も低く、普通の圧力釜じゃ駄目でした。そこで、現地で圧力釜を買って炊いてみたら、炊いた途端はフワっとなって、卵かけご飯なんかにすると結構食べられました。しかし、10分くらいするとすぐにバラッバラになっちゃいましたけどね。
今じゃ、火加減も水加減もボタン一つで全て炊飯器がやってくれちゃいますから、お嫁さんはだいぶ楽になったはずですよ。
『たらちね』は、大家さんが面倒を見て、長屋の独りもんの八っつぁんが嫁を取るという噺です。この嫁、若くて器量良し、ただ丁寧過ぎる言葉遣いが玉に瑕(きず)。
解読不能な嫁との会話に困ってしまう八っつぁん。二人の会話のミスマッチが堪らなく可笑しみがあります。「夫婦の幸せとは、ご飯を一緒に食べること。」八っつぁんは新婚生活を妄想しながら、大声で歌っています。
♪サ~クサクのチンチロリンのポ~リポリ、ザ~クザクのゴーツゴツのバ~リバリ♪
八っつぁん曰く、嫁さんのお茶碗は小ぶりで箸は象牙。まず、茶漬けをたべるにしても、嫁さんは上品にサークサクと食べて、箸が茶碗に当たってチンチロリン。沢庵は小さく切って前歯でポーリポリ。俺の方はでかい茶碗で茶漬けをザークザク、箸が茶碗に当たってゴーツゴツ、沢庵だってでかいのをバーリバリ、となるわけです。
江戸では朝にご飯を炊き、昼と夜は冷や飯か茶漬けなんかにして食べていました。大阪では昼にご飯を炊きます。庶民の食事は一汁二菜が基本。ご飯にみそ汁、お漬物が一品。おかずが付けば上々、お魚が付く日なんてご馳走でした。
尻餅
~年の暮れ、江戸に鳴り響く杵の音~

餅つきは年の暮れの風物詩ともいうべき光景でした。「ぺったん、ぺったん」という杵の音はいかにも景気がよい。あちこちから聞こえてくる餅つきの音で、江戸八百八町、さぞ賑やかだったことでしょう。
大晦日だというのに、餅屋も頼めない貧乏長屋。『尻餅』は、帰ってきた亭主に、ご近所の手前、音だけでも聞かせてほしいと女房が愚痴をこぼすところから噺が始まります。
「えー、餅屋でございます。八五郎さんのお宅はここですな!」と、隣近所に聞えるような大声で、亭主は餅屋の芝居を自作自演で始めます。挙句の果てには、餅をついている音を出すために「おっかあ、臼を出せ」と、女房をうつ伏せにさせると着物をまくりあげ、
手に水をつけてお尻を「ぺったん、ぺったん…。」そのうち、我慢ができなくなった女房はとうとう…
「あの、餅屋さん、あと幾臼あるの?」
「へい、あと二臼です」
「おまえさん、後生だから、あと二臼はおこわにしてもらっとくれ」
僕が子供の頃ころには、お正月の餅は前もって注文しておき、届けてもらうようになっちゃったけど、それ以前は餅つき屋に来てもらい、庭や軒先でついてもらったようです。
餅は正月の必需品のため、年末の餅つき屋は繁盛しました。餅を買うには、十五日までに前もって注文しておく方法と、餅つきに出向いてもらう方法の二種類があり、前者を賃餅(ちんもち)、後者を引摺餅(ひきずりもち)といいます。威勢のいい掛け声に合わせて餅をつく音は、粋でカッコ良いものです。餅つきはパフォーマンス的要素も強く、江戸っ子にとってステイタスの一つでした。餅はハレの日に食べるご馳走です。お正月やお盆、祝い事、新築するときに餅を撒くなんて習わしもあります。正月のお雑煮といえば、餅が欠かせません。お雑煮は地域によって、さらに各家庭によっての食べ方が存在し、面白いものです。
総じて、関東は角餅を焼いた澄まし汁。関西は丸餅と白味噌が多い特徴があるそうです。
我が家は、届けてもらうのは伸し餅、母親の田舎から届けてもらうのは丸餅だったので、両方楽しむことができましたよ。
子別れ<上>
~奥深いお赤飯の歴史~
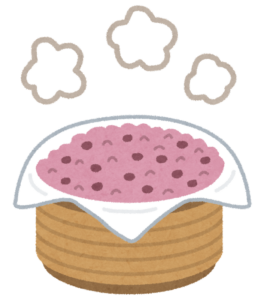
強飯(こわめし)とはもち米を炊いたもので、狭義では赤飯のことを指します。小豆と一緒に赤く炊き、祝いの席で食べることが多いと思います。
しかしかつては、葬式の時には小豆ではなく黒豆入りの強飯を炊くという風習があったそうです。
『子別れ』という落語は上・中・下の三部構成で、上は「強飯の女郎買い」という名で演じられ、今では見かけなくなってしまった葬式の習わしや、赤飯の食文化を窺い知ることができます。
大工の熊五郎は、大店のご隠居の葬式に出かけます。九十歳を超える大往生、これはめでたいというわけで、会葬者へ黒豆入りの強飯と一緒に煮しめを竹の皮で包んだものが配られました。昔、葬式は寺で行うもので、お通夜の翌日、棺桶を担いで寺まで行列していく光景がありました。寺は場末の地、ちょっと外れた所に多くあり、江戸市中から葬式に参列すると、ほとんど一日がかりでした。同じく吉原などの遊郭も外れた所にあったので、葬式の帰りにその足で遊びに行く連中も多くいたわけです。熊五郎もその一人。吉原で珍事件が起きます。
熊五郎のやつ、余った強飯と煮しめを背中や袖、懐にいっぱい背負いこんでいため、煮しめの汁が背中から腹巻…フンドシにも染み込んでしまい大騒ぎ。
結局、熊五郎は吉原に三日も居続けてしまい…、子別れの上はここまでです。
赤飯には、女の子のお祝いというイメージもあるでしょう。女の子のいる家では、初潮になると赤飯が食卓にのぼるなんて慣習があったそうです。その逆もあります。戦前男子は二十歳になると徴兵制で嫌でも兵隊に引っ張られてしまいます。そこで、親が承知の上で、まだ女の人を知らない出征前の若者を遊郭に行かせ、翌朝、御膳に赤飯が出るなんて歴史もあったようです。兵隊に連れて行かれるのは内実は可愛そうだが、表向きはおめでたいことなので、赤飯で盛大に祝ったというわけです。祝い事と弔い、男と女、赤飯の食文化は奥深いものですね。
しわいや
~どケチと梅干し~

「酸っぱい」と思い出しただけで唾液がジュワっと出てきます。梅干しはご飯のお供の代表格です。昔は薬用として用いられ、食用されるようになったのは鎌倉時代に入ってからとされます。
まずは僧侶の酒の肴として愛用され、保存性や殺菌作用もあることから、戦国時代には兵糧として利用されました。庶民の食卓にのぼるようになったのは江戸時代です。梅干しと言えば、アルミニウムのお弁当箱、ご飯の真ん中に梅干し一個だけ。いわゆる「日の丸弁当」は戦争体験者にとっては思い入れがあると思います。『欲しがりません、勝つまでは』『贅沢は敵だ』というスローガンを掲げた戦時中、日の丸弁当は倹約の象徴のようなものでしょう。
落語にはドケチな男というのがしばしば登場し、上方では「始末の極意」、江戸では「しわいや」という題で演じられる噺があります。「しわい」にはケチ、しみったれという意味で、この落語では梅干しの食べ方を通じて、倹約の極意を教える人物が登場します。
一日三食のおかずは梅干しだけという男がいた。まず朝はしゃぶるだけ、昼は二つに割って半分食べ、もう半分は夕飯のおかずに。種はあくる日の三時に金槌で割り、中の実をかじりながらお茶をすする。しわい屋に言わせりゃ「そりゃ、贅沢だねぇ」。上には上がいるものだ。
「一個の梅干しで三週間はもったよ。一週目は全く手を触れない。お膳の上に置いたまま、これをにらんで飯を食ったものだ。梅干しを口の中に入れたら酸っぱいだろうなと思えば、たちまち唾液が出てきて、食も進み、ご飯がのどに詰まることはない。二週目になって、やっとしゃぶり始め、三週目にかじり始める。」
このケチっぷり、ここまで極めれば見事な芸というものです。
酢豆腐
~江戸っ子が考案した米糠の活用法~

江戸っ子にとって、ピカピカの白米が食べられることは自慢です。当時「江戸わずらい」と呼ばれる奇病が流行しました。参勤交代で江戸住まいをした大名がかかり、故郷に帰るとケロっと治ってしまうことから、その名がついたともいわれます。いまでは「脚気」とも呼ばれ、精米によってビタミンB1を含む米糠が取り除かれてしまうことが原因で起こる病です。白米が食べられる江戸っ子ならではの、一種の贅沢病と言うべきか、今でいう生活習慣病のようなものでしょう。
一日三度、主食に米を食えば、もちろん米糠だって大量に生産されます。江戸時代は究極のエコ社会です。米糠だって無駄にしません。搗き米屋から米糠だけを仕入れて、小分けにして売る、糠屋という職業も存在しました。米糠は、洗濯石鹸として利用されました。
銭湯で体を洗うのに使った米糠を買い取る商人さえ存在し、それを農家が買って畑の肥料にしました。そんな米糠を利用した庶民の知恵が、糠みそ漬けです。『酢豆腐』という落語には、糠みその古漬けのきゅうりが登場します。町内の若い男どもが集まり、暑気払いで一杯やろうと話が決まったのはいいものの、酒の肴がない。台所の糠みその底に、きゅうりの古漬けがあったことを思い出し、いざ取り出すとなると・・・
「冗談いっちゃあいけねえ。あれに手を突っ込んだが最後、爪の間に糠みそがはさまって拭こうが洗おうが落ちやしねえ。女の子なんかよけて通らぁ。御免こうむりやしょう」
誰もやろうとしない。そこへ通りがかったお調子者の半公を呼び止め、散々おだてて、頼みをもちかけるも失敗です。糠みそ漬けは発酵食品で、毎日の手入れが欠かせません。
怠ると腐らせてしまいます。余り物の野菜なんかを漬けるのに手軽で、ご飯のおかずとして重宝されました。それにしても、古漬け一つ取り出すのに大騒ぎですね。それに比べて、朝昼晩ご飯を作り、糠みそ漬けにだって臆せず手を突っ込むお母さんは強い。








